PCEデフレーターでドル円はどうなる?日経平均株価や日銀の動向も解説【2024年6月】
2024年6月現在、アメリカのPCEデフレーターの結果を受けて、利下げ期待からドルが下落しやすい展開となりました。本稿では、プロトレーダーの筆者が、2024年6月の市場動向を分析し、PCEデフレーター、日経平均株価、ドル円の展望について解説します。是非参考にしてみてください。
 FXコラム
FXコラム
2024年6月現在、アメリカのPCEデフレーターの結果を受けて、利下げ期待からドルが下落しやすい展開となりました。本稿では、プロトレーダーの筆者が、2024年6月の市場動向を分析し、PCEデフレーター、日経平均株価、ドル円の展望について解説します。是非参考にしてみてください。
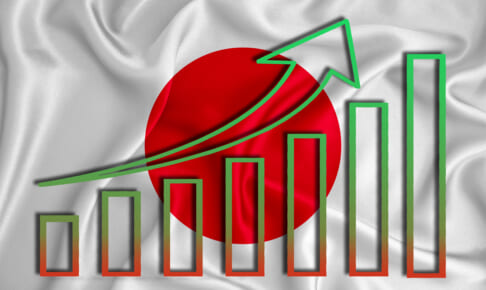 投資信託
投資信託
近年、日本の株式市場では日経平均株価が過去最高値を更新し、大型株に注目が集まっています。しかし、実は中小型株にも魅力的な投資機会が潜んでいるのをご存知でしょうか。本稿では投資のプロである筆者が、中小型株ファンドのメリット・デメリットや、中小型株ファンドを5つ厳選して解説します。
 FXコラム
FXコラム
2024年4月現在、日銀金融政策決定会合を受け、ドル円は一時158円まで急伸しました。政策変更は予想通り据え置きとなったものの、円安を牽制する発言や政策はなく、市場にとってサプライズとなりました。本稿では、プロトレーダーの筆者が、日銀金融政策決定会合や、ドル円の動きを解説します。是非参考にしてみてください。
 株式投資コラム
株式投資コラム
2024年3月現在、日経平均株価が一時4万円を突破し、さらなる上昇が期待されています。本稿ではプロトレーダーの筆者が、日経平均株価の水準をバブル時と比較しながら、今後の上昇余地について検討します。また150円を突破したドル円についても解説しますので、是非参考にしてみてください。
 ESG投資コラム
ESG投資コラム
投資先を決定するうえで、サステナビリティの実施を重視する方も多いでしょう。ドラッグストアに数多く並ぶサプリのメーカーも、ESGの取り組みを数多く行っています。具体例として、包装容器のプラスチック使用料の削減、原材料のリサイクルといった取り組みが挙げられます。今回はカロリミット、ディアナチュラ、ネイチャーメイドでお馴染みの企業の事例を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
 投資・マネーコラム
投資・マネーコラム
2023年6月現在、経平均株価が急上昇しています。最近投資を始めた投資家は、嬉しい悲鳴を上げているでしょう。しかし相場の上昇には、いずれ終わりが来ます。本稿ではプロトレーダーの筆者が、日経平均の上昇局面で注意したいポイントや、2023年の年末までの見通しを解説します。
 FXコラム
FXコラム
2023年4月現在、日本では本決算が終了し、新年度に入りました。3月までの相場が終了し、これまでとは異なる動きが出やすくなる時期でもあります。アメリカでは一旦混乱が落ち着きを取り戻しつつあります。一方で再度インフレ動向に注目が集まる中、4月以降のドル円の動向をプロトレーダーの筆者が解説します。
 投資ニュース
投資ニュース
株式会社ジェーシービー(JCB)とマネックス証券株式会社は8月4日、ロイヤルティプログラムサービス「タネカブ」の本格開発に向け、業務提携に関する基本合意書を締結したと発表した。
 株式投資コラム
株式投資コラム
2022年は世界的にインフレが進行する中、世界的な利上げムードとなっています。
各国がインフレ抑制のため政策金利を急ピッチで引き上げていくことが影響し、世界的に株安が進行する中、今後の動向に不安を覚える個人投資家の方も多いでしょう。ここでは現在の株安のトレンドがどこまで継続し、また今後どのような展開となり得るのか、テクニカル的な側面からチャートを見つつ解説していきたいと思います。
 投資信託
投資信託
マネックス証券株式会社は6月15日、定期レポート「MONEX個人投資家サーベイ」を発表した。6月3日から7日までインターネットで同社の顧客にアンケート調査(回答数1035件)した。定例調査である個人投資家の相場観の調査に加え、特集として「2022年の日経平均株価、ダウ平均株価の高値安値予想」「今後の企業業績にプラスとなるもの」「個人投資家視点の株主優待制度」について調査している。
 投資信託コラム
投資信託コラム
2022年5月現在の株式市場は新型コロナウイルス感染拡大に加えて、米国中央銀行による金融緩和のテーパリング、ロシア・ウクライナ間における紛争、それに伴うインフレーション懸念などがあり、ボラティリティが大きい展開です。今回は日本の代表的な機関投資家が、ボラティリティが大きい局面でどのように動き、株式市場に影響を与えてきたのかを解説します。また環境下において注目すべきセクターも説明します。
 投資信託コラム
投資信託コラム
日経平均に連動することを特徴とする「日経平均連動型」の投資信託やETFは、個別株よりも手軽に分散投資できる金融商品です。主に中長期の保有に向いた商品ですが、日経平均連動型タイプにも様々な銘柄があるため、選び方で悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、日経平均連動型の投資信託やETFの特徴、各銘柄の手数料、過去の成績を詳しくご紹介するので、関心のある方は参考にしてみてください。
 株式投資コラム
株式投資コラム
値がさ株とは、株価の水準が高い銘柄のことです。何円以上という明確な基準はありませんが、1単元(100株)の購入金額が50万円以上、つまり株価が5,000円以上の銘柄を値がさ株と呼ぶのが一般的です。
この記事では、値がさ株の特徴とメリット・デメリットについて解説します。
 株式投資コラム
株式投資コラム
世の中にある代表的な金融資産は株、債券、不動産、商品(コモディティ)、通貨の5つです。この中で通貨だけは特徴が異なり、自国通貨や外国通貨を資産として保有するという目的以外に、他の4つの外国資産を取得する際に為替という形で必ず関係します。資産取得だけでなく、外国資産の為替変動リスクをヘッジするために通貨を先物市場で売る場合もあります。様々な取引がそれぞれの国の参加者の都合で行われるため、資金の流れを全て把握することはほぼ不可能です。しかし世界中から情報収集をして資金の流れを把握し先回りしようとするヘッジファンドなどの投機筋が相場で大きな影響力を持っていることもあり、株などの資産の取引が為替に及ぼす影響を把握しておかなければなりません。今回は資産の中でも代表的な株式市場と、為替市場の関係性について解説していきます。
 FXコラム
FXコラム
米国債市場はアメリカ消費者物価指数を受けて、金利は大幅上昇する動きとなりました。10年金利は1.44%付近から1.58%付近まで上昇しており、短いゾーンから全体的に金利上昇が進行しました。また、20年金利が30年金利を逆転しており、足元はインフレ懸念からの早期利上げ観測は高まっているものの、長期的な経済成長は期待されていないような動きが継続しています。
 FXコラム
FXコラム
2021年10月25日~29日の米国債市場は長期ゾーンを中心に金利低下する展開となりました。金利カーブはベアフラットニングが継続しており、長期債の金利の低下が顕著になっています。ポイントは、初めて米国債30年金利が20年金利を下回り、逆イールドになっている環境です。長期国債の金利が低下しているという状況は、マーケットが今後インフレが進行すると考えられます。インフレへ対応するための政策金利引き上げによって、経済成長が鈍化するということを示唆しており、世界的なインフレ懸念は、マーケットに引き続き警戒感を与えている状況です。しかし、20年金利と30年金利が逆転しているのは過度な反応とも考えているため、再度30年金利をショートして20年金利をロングする選択肢も、トレード戦略では有効と筆者は考えます。
 FXコラム
FXコラム
2021年10月11~15日の株式市場は米国株、日本株ともに大幅上昇する動きになりました。米国では、FOMC議事要旨にて年内テーパリングが確認される中、9月消費者物価指数の影響を受けたことにより過度なインフレ懸念が後退しました。金曜日の予想以上の小売売上高や決算発表が良好だったことを受け、シクリカル銘柄(景気敏感株)が物色される中、ディフェンシブ銘柄は向かい風となっています。10月18日週の注目する経済指標は18日に米鉱工業生産・設備稼働率、20日のベージュブックが公表される予定となっています。米国ではインフレ懸念が後退し始めており、米国債は短期金利を中心に上昇してきていることから、ドルインデックスはある程度楽観的な部分を織り込んでいると考えても良いのではないでしょうか。
 投資信託
投資信託
マネックス証券株式会社が9月21日発表した「MONEX個人投資家サーベイ 2021年9月調査」で、現状の日経平均株価に対する評価は同月初旬の株価急上昇の影響が早くも表れた。調査は9月10日から13日にかけ同社の口座保有者へアンケートを行い、回答数1117件の回答を得た。
 投資信託
投資信託
6月に入り乱高下する日経平均株価で、マネックス証券株式会社の調査「MONEX個人投資家サーベイ」では、日経平均株価(調査実施時 2万9000円程度)への評価は「非常に高い」「高い」との回答を合わせ約51%で、前回調査の約71%から大きく低下した。
 株式投資コラム
株式投資コラム
欧米では株価が上昇し、5月に入って米国のNYダウやイギリスのFT100指数、ドイツのDAX指数などは、過去最高値圏にあります。しかし、日本の株価は上値が重くなっています。この差は、新型コロナワクチン接種率の差が原因の1つと考えられています。
日本株はワクチン接種によってどうなるのか、今後の展望について解説します。