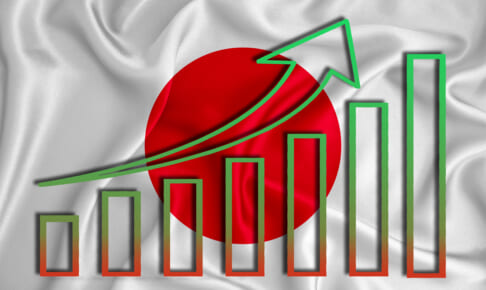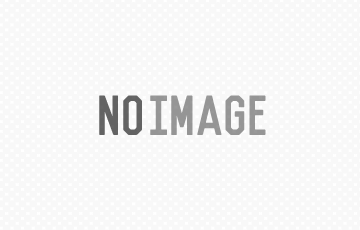投資のプロがサステナブル投資をするなら?おすすめの日本株や投資信託も解説
世界的にサステナブル投資への関心が高まっています。サステナブル投資とは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の要素を考慮した投資手法で、ESG投資とも呼ばれます。この投資手法は、長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指すものです。本記事では、NISAでサステナブル投資にチャレンジしたい読者に向けて、日本株や投資信託の選び方やおすすめの銘柄を解説します。投資のプロである筆者がサステナブル投資をするならどのような点に注目するのか、ポートフォリオ構築の考え方も踏まえて説明します。