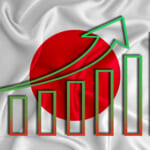NISAは運用益に対して税金がかからないため、資産形成を目指す人なら積極的に利用したい制度です。しかし、デメリットや注意点を理解しないで始めると損をする可能性もあり、注意が必要です。
この記事では一般NISAのデメリットや注意点とその対策、一般NISAでの投資に向く人を解説します。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定サービスの利用を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
※この記事は2022年5月13日時点の情報に基づき執筆しています。最新情報はご自身にてご確認頂きますようお願い致します。
目次
- 一般NISAとは?
1-1.一般NISAの投資対象 - 一般NISAのデメリット・注意点
2-1.非課税期間は5年まで
2-2.損益通算・繰越控除ができない
2-3.利益が出ていないのに課税される場合がある
2-4.ロールオーバーするとその年の非課税枠が減る
2-5.2024年から新NISAになる
2-6.すでに保有している商品を移管できない
2-7.売却すると非課税枠を再利用できない
2-8.使い切れなかった非課税枠を繰り越せない - 一般NISAのデメリットへの対策
3-1.見込みがなければ損切りする
3-2.長期保有・分散投資
3-3.投資信託を活用する
3-4.なるべく非課税枠を使い切るようにする
3-5.現行の一般NISAのうちに始める - 一般NISAの利用メリットがある人
4-1.収入から投資に回すお金に余裕がある人
4-2.預貯金などの余裕資金のある人
4-3.自分の投資スタイルがある人
4-4.投資に時間をかけられる人
4-5.株式投資などで比較的大きな利益を狙う人 - まとめ
1.一般NISAとは?
NISA(少額投資非課税制度)とは、国民の資産形成をサポートするために投資で得た利益を非課税にする制度です。
通常、株式や投資信託を買って配当金や分配金を受け取ったり、売却益を得たりすると、20.315%の税金がかかります。しかし、NISA口座で買い付けた商品から得た運用益には課税されません。
たとえば、特定口座などの課税口座で、100万円で購入した株が150万円に値上がりしてから売却したとします。売却益の50万円には約10万円の税金がかかるため、受け取れる利益は約40万円になります。
この株をNISA口座で取引すれば、利益の50万円を全額受け取れるというわけです(手数料等は考慮していません)。
現在、NISAには次の3種類があります。
- 一般NISA
- つみたてNISA
- ジュニアNISA(2023年で終了)
このうち、一般NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が最長5年利用できます。
1-1.一般NISAの投資対象
一般NISAの非課税投資対象は、主に以下のような金融商品です。
- 上場株式
- ETF
- 公募株式投信
- REIT
NISAでは多くのネット証券で、株の取引手数料や投資信託の購入手数料が無料になっています。
2.一般NISAのデメリット・注意点
投資で比較的大きな利益を狙う人などに、一般NISAは魅力的な制度です。しかし、利用するならデメリットも理解しておく必要があります。
2-1.非課税期間は5年まで
一般NISAの非課税投資期間は、最長5年です。非課税期間満了後のNISA口座の資産の扱いには、次の3つの選択肢があります。
- ロールオーバー
- 非課税期間中に売却
- 課税口座へ移管
ロールオーバーとは?
ロールオーバーとは非課税期間が終了するNISAの資産を、翌年の非課税枠に移管することです。ロールオーバーにより、非課税期間が5年延長されます。運用商品にさらなる値上がりが見込める場合などに有効な方法です。
ロールオーバーは同じ金融機関で購入した商品でないとできないため、金融機関を変更した人は選択できません。その場合、金融機関を元に戻す手続きが必要です。
2-2.損益通算・繰越控除ができない
NISAで損失が発生した場合、他の口座の利益と損益通算できません。損益通算とは利益と損失を相殺することで、課税所得が減る節税効果があります。
たとえば、特定口座で株の売却損が5万円あった人が、同じ年に配当金を10万円受け取っていたとします。その場合、配当金と売却損は相殺され、払いすぎた税金が還付されます。
しかし、NISA口座で売却損が出て特定口座で配当金を受け取っていた場合、損益通算の対象とはならないのです。よって、実際の利益より多く課税されることになります。
また、通常は損益通算で引き切れない損失が残った場合には繰越控除により、翌年以降の運用益から差し引けます。しかし、NISAでは繰越控除も適用されません。
NISAでは損益通算・繰越控除ができないため、運用益が出なかった際にはメリットが得られないというわけです。
2-3.利益が出ていないのに課税される場合がある
NISAでは実際に利益が出ていなくても課税されるケースがあり、注意が必要です。それは非課税期間終了後に、値下がりした資産を特定口座などの課税口座に移管するケースです。課税口座へ払い出すと、移管時点での時価が取得価格となります。
たとえば、NISA口座で70万円で買って50万円に値下がりした株を特定口座に移管すると、50万円で買ったことになるのです。その後60万円で売却すると実際には10万円の損失なのに、10万円の利益が出たとして課税されてしまいます。
NISAで買った運用商品が値下がりしたまま非課税期間が終わりそうなときは、対策を考える必要があるのです。
2-4.ロールオーバーするとその年の非課税枠が減る
一般NISAの非課税期間終了後に運用資産をロールオーバーすると、その年分の非課税投資枠が使われます。
一般NISAで、80万円で購入した株が5年後に100万円になっていたとします。この株をロールオーバーするとその年の非課税投資枠を100万円使い、新規で投資できる金額は20万円になるというわけです。
ロールオーバーは保有する資産の一部のみも可能です。たとえば株式を2銘柄持っている場合、1銘柄をロールオーバーし、残りを売却なども選べます。
また、NISAで買い付けた商品が値上がりして120万円以上になっても、全部のロールオーバーが可能です。その場合、その年の非課税枠を使い切り、新規投資はできなくなります。
2-5.2024年から新NISAになる
2024年から一般NISAは新NISAに改正されます。新NISAの非課税投資枠は、以下のような2階建てとなります。
- 1階部分:年間非課税限度額20万円の積立投資枠
- 2階部分:年間非課税限度額102万円の通常買付・積立投資枠
2階部分はこれまでの一般NISAと同様の運用ができますが、そのためには1階部分の積立投資をすることが条件となります。ただし、今の一般NISAをしていた人などは、新NISAで1階での積立投資をしなくてもかまいません。
2-6.すでに保有している商品を移管できない
NISAの非課税対象は新規買付のみで、NISA口座開設前から保有している商品は移管できません。一般NISAはつみたてNISAに比べると投資経験のある人向けですが、すでに含み益がある商品などの移管はできないというわけです。
2-7.売却すると非課税枠を再利用できない
NISAの運用商品を売却すると、その非課税枠は再度利用できません。複数の銘柄で分散投資をする人の多くは、定期的にリバランスを行います。リバランスでは値上がりした商品を売却して、値下がりした商品を買い付け、各商品への投資割合を一定に保ちます。
NISAでは、売却した商品の非課税枠が使えなくなるため、買付には新しい非課税枠が必要です。その年の非課税枠が残っていなければ、リバランスの買付はできません。
2-8.使い切れなかった非課税枠を繰り越せない
NISAではその年度で使わずに残った非課税枠を翌年以降に繰り越せません。今年50万円しか買い付けなかったとしても、翌年の非課税枠は190万ではなく120万円のままです。
3.一般NISAのデメリットへの対策
以上の一般NISAのデメリットには、対策可能なものもあります。ここでは、一般NISAのデメリットを避ける方法を紹介します。
3-1.見込みがなければ損切りする
一般NISA買った株などが期待通りに値上がりしない場合、損切りも視野に入れましょう。NISAは中長期の資産形成に適した制度のため、買い付けた商品はなるべく長期保有するのが望ましいとされます。しかし、非課税期間満了時に含み損がある状況では、その後の対応が難しくなります。
そこで、特に値下がりした個別株などが値上がりする見通しがなければ、損失が少ないうちに売却するのも選択肢の1つです。一般NISAで通常買付をするなら、積立のような「ほったらかし」はできないと考えましょう。
3-2.長期保有・分散投資
NISAでは非課税期間終了時までに運用益が出ていないとメリットがなく、その後の対応が難しくなります。そのため、リスクコントロールをして、着実に利益を出すことが大切です。投資経験の少ない人が運用益を出していくには、長期保有と分散投資が有効です。
また、一般NISAでも積立ができるので活用するとよいでしょう。必ず利益が出る保証はありませんが、短期的な値動きにとらわれずに運用を続けることが資産形成につながります。
3-3.投資信託を活用する
NISAでは非課税枠の再利用ができずリバランスが難しいため、投資信託の活用が有効です。投資信託は分散投資のための金融商品で、複数の銘柄を運用のプロが買い付けてくれます。リバランスも自動的に行われるため非課税枠を使ってしまう心配がなく、取引の手間もかかりません。
投資信託の中には株式や債券など複数の資産に投資する、バランスファンドもあります。手間をかけずにNISAで分散投資がしたい人には、バランスファンドは強い味方となります。
3-4.なるべく非課税枠を使い切るようにする
NISAでは使わなかった非課税枠を繰り越せません。少額からの投資も可能ですが、多くの資金を回したほうが資産の運用効率は高まります。一般NISAの年間120万円の非課税枠が大きく余るようであれば、つみたてNISAでの運用を検討してみましょう。
3-5.現行の一般NISAのうちに始める
2024年からの新NISAで上場株式投資だけで1階部分の積立をしたくない人は、現行の一般NISAを利用するほうが得策です。すでに一般NISAをしている人が上場株式だけを購入する場合には、2階部分のみを利用できるからです。
ただし、監理銘柄や整理銘柄に指定されているものは、新NISAでは購入できません。
4.一般NISAの利用メリットがある人
一般NISAは幅広い人にメリットがあり、「やらないほうがいい人」は多くありません。ここでは、一般NISAが特に適した人を解説します。
4-1.収入から投資に回すお金に余裕がある人
一般NISAの1年間の非課税限度額は120万円と、つみたてNISAより大きな枠です。収入が多い人や生活費がかからない人など、投資に多くのお金を回せる人は一般NISAに向いています。毎月の給与から積立、ボーナスで通常買付を組み合わせるなど、非課税枠を有効に活用しましょう。
4-2.預貯金などの余裕資金のある人
預貯金などで一般NISAの非課税枠を大きく上回る余裕資金のある人も、一般NISAの非課税投資が適しています。一般NISAは投資対象の選択肢が多いため、投資経験がある人も初心者の人も自分に合った投資が可能です。
余裕資金はあるものの投資経験がない人なら、リスクが低めの投資信託などで手堅く始めてもよいでしょう。
4-3.自分の投資スタイルがある人
IPO(新規公開株)投資や配当金狙いなど、すでに投資経験があって自分のスタイルがある人には、一般NISAが有効です。自分のやり方である程度の運用益が見込める人が一般NISAを活用すれば、非課税メリットを享受できるからです。
非課税限度額分だけでも課税されなければ、それだけ運用益の手取りは多くなります。
4-4.投資に時間をかけられる人
株式やETFなど市場で取引する運用商品は、売買のタイミングを考えなければなりません。そのため、注文や値動きのチャートやニュースを調べるなどの手間や時間が必要です。一般NISAで日常的に株式などの市場取引をするなら、時間に余裕のある人が適しています。
仕事や育児で投資の時間がない人は、つみたてNISAを選ぶほうが無難です。
4-5.株式投資などで比較的大きな利益を狙う人
一般NISAはつみたてNISAと異なり、株式にも投資できます。株式は投資信託やETFと比べるとリスクが大きく、うまくいけば数年で大きく企業が成長し株価が上昇する銘柄もあります。企業の業績や将来性などから有望な銘柄を見つけるのは簡単ではありませんが、大きな利益を狙う場合には一般NISAが適しています。
まとめ
一般NISAは投資対象がつみたてNISAに比べて幅広く、1年間の非課税限度額も120万円と大きくなっています。どちらかといえば、投資経験者や余裕資金のある人向けの非課税制度といえます。
活用にあたってはデメリットもよく理解し、着実に利益が得られるように運用していきましょう。
松田 聡子
最新記事 by 松田 聡子 (全て見る)
- 個人の金融資産が2212兆円の過去最高を突破。将来に向けた資産形成のポイントは? - 2024年10月21日
- 高校生が金融教育で学ぶ「貯める・増やす」資産形成の内容は?NISAの仕組みも - 2024年8月8日
- ウェルスナビとROBOPROの違いは?手数料や実績、メリット・デメリットを比較 - 2024年6月22日
- 2024年度の税制改正で子育て世帯はどう変わる?家計のポイントを5つ解説 - 2024年6月9日
- NISAで毎月いくら積立設定するべき?収入や年齢からポイントを解説 - 2024年6月9日