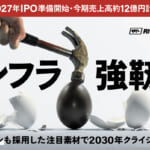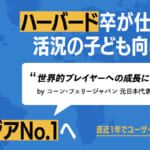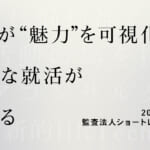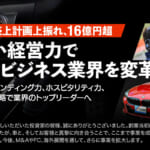株式投資を始めるには、証券口座の開設が必要です。しかし、証券口座を開設できる証券会社はたくさんあるため、どの証券会社を選べばいいかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、大手証券会社やネット証券会社など、主要な証券会社の特徴や取扱銘柄、手数料などについて比較してみました。証券会社選びの参考にしてみてください。
(記事監修者:藤井 理)
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・銘柄への投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
※本記事は2024年2月20日時点の情報をもとに執筆されています。最新の情報については、ご自身でもよくお調べの上、ご利用ください。
目次
- 証券会社とは?
1-1.証券会社の種類
1-2.店舗証券とネット証券の大きな違いとは? - 店舗を持つ大手3大証券会社の比較
2-1.SMBC日興証券の特徴
2-2.野村證券の特徴
2-3.大和証券の特徴 - 株が買えるネット証券会社7社の比較
3-1.マネックス証券
3-2.SBI証券
3-3.松井証券
3-4.PayPay証券
3-5.DMM株
3-6.楽天証券
3-7.auカブコム証券の特徴 - まとめ
1.証券会社とは?
証券会社とは、私たちが株式を買ったり売ったりするときの取次をしてくれる会社のことをいいます。
株式投資を始める場合は、株式を購入するための資金を預けたり、株式の配当を受けたりするための証券口座が必要になります。
その証券口座は証券会社が提供しています。そして、証券会社によって売買に掛かる手数料や取り扱っている商品、利用できるツールなどに違いがあります。
そのため、どの証券会社で証券口座を開設するのか、ということが大切になるのです。
1-1.証券会社の種類
証券会社の区分としては、大手証券、中堅証券、地場証券、ネット証券があり、地場証券には地域密着型の証券会社も存在しています。
また、証券会社の営業スタイルは大きく分けて2つの種類があります。1つが、店舗を構えてサービスを提供している「店舗型証券会社」です。野村證券やSMBC日興証券などのいわゆる大手証券会社の多くは店舗型となります。店舗型証券会社は全国各地に支店を構えており、対面による営業スタイルが主流であるという特徴があります。
もう1つが、オンラインでのみ株取引サービスを提供する「ネット証券会社」です。SBI証券やPayPay証券などがネット証券に当たります。インターネットの発展とスマホなどの普及に伴って急激にネット証券の市場が拡大しています。
1-2.店舗型証券とネット証券の大きな違いとは?
店舗型証券では、店舗での対面営業が特徴であると解説しました。そのため、店舗に足を運んだり、自分の担当者に連絡したりすれば、株式投資に関してこまめに相談ができるというメリットがあります。
ただし、それだけ人件費が発生することになるため、取引に必要な手数料はネット証券と比べると高めに設定されています。
一方、ネット証券の場合は口座開設や売買の注文など、必要な手続きをすべて自分で行う必要があります。ただし、担当者など仲介者を通す必要がないため、取引に掛かる手数料が安く抑えられるというメリットがあります。
このような違いがあるということを理解したうえで、自分の投資スタイルにあった証券会社を選ぶことが大切です。売買を頻繁に繰り返す投資スタイルであれば手数料が安いネット証券を、運用にあたり、証券会社のアドバイスが必要な場合には店舗型証券を選ぶとよいでしょう。なお、店舗証券・ネット証券に関わらず、証券会社では資産が分別管理されているため、証券会社が破綻して返済が困難となった場合は、基金から1顧客当たり1000万円を上限に補償されます。
それでは、各証券会社の特徴について特徴を見ながら比較をしていきましょう。
2.店舗を持つ大手3大証券会社の比較
まずは、主要な店舗型証券の特徴から紹介します。
今回取り上げる店舗型証券は、日本の大手証券会社といわれている以下の証券会社3社です。
- SMBC日興証券
- 野村證券
- 大和証券
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。(下記記載の手数料などはすべて2024年2月20日時点の情報となります)
2-1.SMBC日興証券の特徴
SMBC日興証券は、三井住友フィナンシャルグループの会社で日本全国に120を超える店舗を展開している大手証券会社の1社です。
SMBC日興証券の強みは、ほかの主要証券会社と比較して取引手数料が安く抑えられることです。ダイレクトコースで口座開設をすれば、国内現物株式取引の手数料は以下のようになります。
- 10万円まで:137円(税込)
- 20万円まで:198円(税込)
- 50万円まで:440円(税込)
- 100万円まで:880円(税込)
一方、ダイレクトコースでは信用取引の約定金額に関わらず、取引手数料は無料となります。
また、SMBC日興証券では、運営する記事から株が買える「日興フロッギー」というウェブサービスも提供しています。日興フロッギーでは、株は100円から購入することができ、購入手数料も100万円以下は無料(売却手数料は0.5%)となっているため、コストを抑えて少額投資を始めやすく投資初心者にも人気があります。
日興フロッギーではdアカウント情報を入力して連携することで、dポイントがあれば100ptから株を購入できるサービス「日興フロッギー+docomo」も提供されています。「日興フロッギー+docomo」では、「+3 dポイント」のアイコンがついている記事を読むだけで、3ptが貯まるのも特徴です。ポイント投資やポイ活に興味があるという方も検討されてみると良いでしょう。
SMBC日興証券が提供する「日興フロッギー」
2-2.野村證券の特徴
野村證券は業界の中でも財務規模などが特に大きい証券会社で、強みは調査能力や情報収集能力が高いことです。かつて、前身の野村商店に調査部が設立され、その調査内容を顧客に無料配布していた流れが現在でも受け継がれており、野村證券のことを「調査の野村」と呼ぶこともあるくらいです。
また、国内株式を始め、海外株式、投資信託、債券、NISA(少額投資非課税制度)、iDeCo (個人型確定拠出年金)、ETF、REIT、FX、不動産ST(セキュリティ・トークン)、ESG投資など、金融商品と呼ばれるものの多くを取り扱っているため、投資対象の選択肢の幅を広くすることができます。さらに、IPO(新規公開株式)の抽選にも強く、実際の引き受け金額や主幹事案件でも常時トップクラスの実績があります。
野村証券の国内現物株式取引手数料は、約定代金によって異なります。オンライン専用の取引の場合、10万円までが152円(税込)、10万円超~30万円までが330円(税込)、30万円超~50万円までが524円(税込)となります。信用取引の場合は、約定代金に関わらず1注文あたり524円(税込)です。
豊富な情報をもとに株式投資をしたい場合や、対面による丁寧なサービスを受けながら資産運用を始めたい方、IPO株にチャレンジしたい場合に利用を検討してみると良いでしょう。
2-3.大和証券の特徴
大和証券も、日本の大手証券会社の1つです。大和証券の強みは、大手証券会社ならではの取扱商品の多さと提供しているサービスの幅の広さです。
こちらも国内株式から、海外株式、FXなどさまざまな金融商品を取り扱っていることに加え、IPOにも強みを持っているので、初値売りによるキャピタルゲインを目指す方にも向いています。
また、忙しくて資産運用に取り組む余裕のない方や、将来に不安を感じる方には、投資を一任して運用してもらえるラップ口座も向いています。大和証券のラップ口座は、2004年に取り扱いを開始してから契約資産残高は3兆円を超えるなど幅広く支持されています。
さらに、国内現物株式取引手数料にも特徴があり、1日の約定合計金額が300万円までは、委託手数料が3,300円(税込)で取引し放題になる「ハッスルレート」というサービスを提供しています(「ダイワ・ダイレクトコース」のオンライントレードの場合)。
信用取引での手数料は売買代金50万円までなら1回314円(税込)、50万円を超えた場合も一律524円(税込)とかなり低額になっているので、信用取引を安く始めたい方にはメリットがあります。
株式投資以外の幅広い投資を行いたい場合や、大手証券会社のなかでも手数料を抑えたい場合に選択肢の一つとして考えてみると良いでしょう。
3.株が買えるネット証券会社7社の比較
次に、株式が売買できるネット証券会社の特徴について紹介します。今回は、以下の7つのネット証券を取り上げます。
- マネックス証券
- SBI証券
- 松井証券
- PayPay証券
- DMM株
- 楽天証券
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1.マネックス証券の特徴
マネックス証券は1999年の設立当初からオンラインでの金融取引を運営しており、2024年1月末時点で総口座数は約257万の証券会社となっています。
幅広い金融商品を取り扱っていることが大きな特徴で、国内株式だけでなく外国株式、FX、投資信託、債券、おまかせ運用(ON COMPASS)などの金融商品も取り扱っており、中でも米国株式の取り扱い銘柄数は5,000超、中国株に関しては2,000超の取り扱いがあり、香港証券取引所に上場しているほとんどの銘柄で取引を行えます。なお、米国株は1株から購入できるため、投資額も数千円から始められるメリットもあります。
手数料については、国内株式の取引毎手数料コースにおける現物取引手数料が、5万円以下は55円(税込)、3,000万円超は1,070円(税込)となりました。
注文方法の選択肢が多数あることも、マネックス証券の良いところです。他社では成行・指値注文のみという証券会社も多い中、逆指値注文などができるという強みがあります。
逆指値注文とは、通常の指値注文とは逆に、価格が特定の水準を上回ったり下回ったりしたときに取引を行う注文方法です。例えば、トレンドに追随して購入しようとする「順張り」の戦略を取りたい場合や、損失を最小限に抑えるため、株価が一定以上に下落したら売る「損切り」に役立つので、幅広い取引戦略を取ることができます。
3-2.SBI証券の特徴
SBI証券はグループ全体の口座数が1,200万を突破するなど、ネット証券のなかでもトップクラスで利用者数が多い証券会社です。SBI証券にはさまざまな特徴がありますが、特に際立っているのは以下の3つです。
- 手数料が格安であること
- 提供しているツールが高機能であること
- IPO取引にも強いこと
SBI証券では、中長期投資におすすめの「スタンダートプラン」とデイトレードにおすすめの「アクティブプラン」の2つの手数料体系が用意されています。特にアクティブプランは、約定代金に関わらず手数料無料となっており、取引コストを最小限に抑えたい方にメリットが大きくなっています。途中でプラン変更も可能ですので、幅広いニーズに応えることができます。
また、SBI証券が提供している株式売買ツール「HYPER SBI」は、板情報画面からドラッグ&ドロップのマウス操作で発注や取消を行える操作性の高さや、豊富なマーケット情報などが特徴です。
なお、HYPER SBIおよびメインサイトで利用できる全板サービスは1か月330円ですが、取引状況や口座状況により無料で利用できる場合もあります。
SBI証券では、様々な取引や投資信託保有額に応じてポイントが貯まるのも特徴です。Tポイント、Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALのマイル、PayPayポイントなどに対応しており、1ポイント=1円として国内株式(現物・S株)や投資信託の買付にも利用できるなど、ポイント投資も可能です。
さらに、投信積立をクレジットカードで決済できる「クレカ積立」が可能です。対応しているクレジットカードは三井住友カードとなっており、一度設定すれば自動で引き落としてくれるため手間がかからず、積立額の最大5.0%のVポイントを貰えます。
※毎月の積立額の上限は5万円です。
※三井住友カードつみたて投資のご利用金額は、プラチナプリファードの新規入会&利用特典、継続特典の付与条件であるご利用金額の集計対象となりません。
新NISA口座(NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠)と併用すれば、長期間に渡って非課税の恩恵を受けつつ、ポイントを貯めることができます。
ネット証券のなかでもIPOの取り扱い実績がトップクラスであることもSBI証券の強みです。大手証券会社の実績にも比肩する水準ですので、ネット取引でIPO株の当選を目指す方には有力な選択肢の一つとなるでしょう。
3-3.松井証券の特徴
松井証券は、創業は大正7年と長い歴史を誇りながら、常に新しいサービスを提供し続ける証券会社で、日本で初めてネット証券を始めた証券会社としても知られています。
松井証券の特徴も手数料が低水準であることと、利用できるツールが高性能であることです。
松井証券では1日の約定金額の合計によって手数料が異なるボックスレートを採用しています。26歳以上の場合、1日の約定金額の合計が50万円以下なら、手数料は無料となっています。一方、25歳以上の場合は約定代金に関わらず、手数料無料です。
ただし、50万円を超えるトレードの場合、100万円までは1,100円の手数料となるなど、ほかの証券会社より手数料が割高になることがあるので、しっかり確認しておきましょう。
このほか、信用取引でデイトレードを行う場合、約定金額に関係なく手数料はすべて無料であり、新NISA口座での取引の場合も、日本株、米国株、投資信託で購入・売却にかかる手数料は全て無料です。
投資信託を預けているだけで、ポイント(松井証券ポイント)を毎月還元してもらえるのも松井証券の特徴です。ポイント還元の対象となる銘柄は、低コストのインデックス投信からアクティブ投信まで全銘柄で、ポイント還元率は業界最高水準となる年間最大1%です。松井証券ポイントは、1ポイント=1円として、dポイント、PayPayポイント、Amazonギフトカードへの交換が可能です。
そして、松井証券で証券口座を開設すると、高性能で最新型の「ネットストック・ハイスピード」というトレードツールを無料で利用することができます。
また、QUICKリサーチネットという株式投資情報サービスを無料利用できるのも松井証券の特徴です。アナリストが厳正中立な立場で企業に関する投資情報レポートをはじめとして、トレンド追跡、IPO情報、決算関連情報など、ほかの証券会社では有料にて提供されていることもあるサービスを松井証券なら口座を開設していれば無料で利用可能です。
このような特徴から、少額での取引が多いという方や、さまざまな投資情報を無料で見たいという方にメリットのある証券会社となっています。
3-4.PayPay証券
PayPay証券は、スマートフォンから簡単に少額で株式投資ができるネット証券会社です。
株式取引は、本来、100株=1単元とした単元株数単位の取引となりますが、PayPay証券では金額単位での取引が可能になっており、1,000円から株式取引を始めることができます。また、アプリから3タップで株式を購入できる手軽さも特徴の1つです。
さらに、日本株や米国株といった株式取引のほかに、1,000円から始められる積立投資「つみたてロボ貯蓄」や、証拠金1万円からデイトレードができる「PayPay証券10倍CFD」、1株からIPO投資ができる「誰でもIPO」など、さまざまなサービスを提供しています。
また、PayPay証券では、貯まったPayPayポイントですぐに投資を始められます。1ポイント=1円で全商品・全銘柄の買付に利用可能です(最低購入金額100円以上1単位)。PayPayポイントが貯まっていれば現金を使わずに投資できるだけでなく、銘柄によっては分配金や配当金を受け取ることができます。
一方で、株式投資において頻繁に利用される指値注文(=価格を指定して注文する方法)が利用できないことや、手数料は基準価格に0.5%を乗じた価格となるため、投資金額が大きくなるほどコストも高くなりやすい点に注意しましょう。
3-5.DMM株の特徴
DMM株は、DMM.com証券が提供する株式取引です。DMM株の特徴は手数料が安いことです。国内株式の現物取引の場合、約定金額が5万円までなら手数料は55円(税込)となっています。
また、約定金額が300万円を超えたとしても手数料は880円(税込)であるなど、業界内でもかなり低水準なだけでなく、手数料に対して1%のDMM株ポイントを付与してもらえます。
25歳以下の場合、国内現物株式取引の手数料が実質無料です。月の第一営業日から最終営業日までの約定で発生した対象取引の手数料全額を【DMM 株】口座に入金してもらえるので、例えば、月末時点の手数料が1,100円だった場合、翌月20日に1,100円がキャッシュバックされます。
このほか、信用取引の場合なら300万円を超える約定でも手数料は無料になります。そのため、1日の取引が少ない方や、高額の信用取引を行う方にはメリットが大きい証券会社です。
米国株式取引の場合は、約定代金に関わらず一律無料ですが、売買時の為替スプレッドとして1ドルあたり25銭かかります。なお、DMM株では、1つのアプリで国内株式と米国株式を取引可能な手軽さが特徴で、米国株式を国内信用取引の担保にすることもできます。
さらに、米株式市場や世界経済の動向を把握できる投資レポートの「バロンズ・ダイジェスト」が無料で提供されているので、株式投資が初めての方も学びながら投資判断に役立てることができます。
DMM株はツールの操作性も高く、特にDMM株のスマホアプリは外出先でも簡単に取引をすることができます。パソコン版のトレードツールもスタンダード版とプロ版の2つが用意されており、自分が使いやすいようにカスタマイズして使用可能です。
3-6.楽天証券の特徴
楽天証券は、ネットショッピングや携帯電話など、さまざまな事業を展開している楽天が手掛けるネット証券会社です。
楽天証券の特徴は、トレードツールの人気が高いことと、楽天グループならではの強みを持っているということです。
楽天証券のトレードツール「マーケットスピードⅡ」では、四季報や日経テレコン21など豊富な情報をすべて無料で閲覧することができます。特に、国内最大級のデータベースである日経テレコン21は単体で利用を申し込むと月額8,000円の基本料金がかかります。それが無料で利用できるのは投資家にとって大きなメリットとなるでしょう。
また、自分が使用しやすいようにカスタマイズできるのも特徴の1つです。必要な情報をすぐに取得することができるうえ、これまでにトレードツールを使っている方でもすぐに代用することが可能ですし、いくつもモニターを並べたりする必要もありません。さらに、ツールの利用料金も無料となっており、楽天証券の口座を持つ方ならだれでも使用可能です。
また、楽天証券の国内株式取引手数料(現物・信用)は、約定代金に関わらず無料です。手数料100円ごとに楽天証券ポイントが貯まっていく仕組みになっています。もちろん、ポイントは楽天スーパーポイントに交換することも可能です。
さまざまなサービスに利用できるポイントが貯まっていくため、楽天経済圏のサービスを頻繁に利用するという方には、メリットや特典が多くなるといえます。
3-7.auカブコム証券の特徴
auカブコム証券は、三菱UFJフィナンシャルグループのネット証券会社です。auカブコム証券の特徴は、国内現物株式の手数料が100万円まで無料(1日定額手数料コースの場合)、25歳以下の現物株式手数料が無料といった点に加えて、1日定額手数料コースであれば1日の合計約定代金100万円まで信用取引手数料が0円、買方金利・貸株料も業界最低水準、投資信託は全ファンドが購入時手数料無料のノーロード商品です。
加えて、50歳以上の方は年齢に応じて現物株・信用取引手数料(一日定額手数料コース)が2%~4%割引される「シニア割引」、auカブコム証券でNISA口座を保有している方の国内現物株・信用取引手数料(一日定額手数料コース)が最大5%割引になる「NISA割」など、割引サービスも多数用意されています。
また、auカブコム証券では、「逆指値注文」「W指値注文」「リレー注文」など、ほかの証券会社では利用できない特殊注文も利用できる可能性があります。
25歳以下の方や少額の現物株投資をメインに考えている方、デイトレや信用取引を中心に検討している方にとってメリットの多いネット証券会社と言えるでしょう。
まとめ
今回は、主要証券会社の特徴について比較しました。取引手数料や提供しているサービス、ツール、投資に関する情報など、証券会社によって特徴や強みは異なります。
本記事を参考に自分に合った証券会社を検討してみて下さい。
藤井 理
大学を卒業後、証券会社のトレーディング部門に配属。転換社債は国内、国外の国債や社債、仕組み債の組成等を経験。その後、クレジット関連のストラテジストとして債券、クレジットを中心に機関投資家向けにレポートを配信。証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト、AFP、内部管理責任者。
- 外国株(米国株など)が買えるネット証券会社
- IPO投資に強い証券会社、少額からIPOに参加できるサービス
- 25歳以下の現物株式の取引手数料が実質0円の証券会社
- 大手証券会社が提供している株式投資サービス
- 少額で株式投資ができるサービス
山本 将弘
最新記事 by 山本 将弘 (全て見る)
- CREAL(クリアル)の評判・口コミ・実績は?メリット・デメリット、利回りも - 2025年6月24日
- COZUCHI(コヅチ)で不動産投資、メリット・デメリットは?他社比較も - 2025年2月3日
- 不動産クラウドファンディングの市場規模は?件数・出資額や成功事例も - 2024年9月9日
- 金(ゴールド)投資信託のメリット・デメリットは?購入可能な証券会社も - 2024年5月27日
- 株初心者が知っておきたい売り板・買い板の見方、板を分析するメリットも - 2024年5月27日