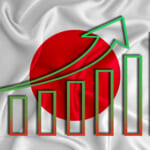積立投資を検討したものの、どのくらいの周期で買い付けたらいいのか迷っているという方もいるのではないでしょうか。
証券会社では、毎月の積立を中心に、毎週、毎日と買付サイクルを選択できるサービスが増えています。この記事では、買付サイクルの違いによる特徴と、毎日積立のサービスを提供している証券会社をご紹介します。毎日または毎月の積立頻度で迷っているは参考にしてみてください。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
目次
- 投資信託の積立、毎日と毎月どちらが良い?
1-1.運用成果はあまり変わらない
1-2.積立頻度より運用期間の長さが大切 - 投資信託を毎日積立するメリットとデメリット
2-1.毎日積立のメリット
2-2.毎日積立のデメリット - 投資信託を毎日積立できる主な証券会社
3-1.SBI証券
3-2.楽天証券
3-3.マネックス証券
3-4.松井証券
3-5.大和コネクト証券
3-6.大和証券 - 投資信託を毎日積立する場合、NISAのつみたて投資枠と成長投資枠のどちらがいい?
4-1.色々な投資信託に投資したい場合は成長投資枠
4-2.より長期の積立・分散に適したファンドを選びたい場合はつみたて投資枠 - 投資信託を長期視点で保有して資産形成をするコツ
5-1.投資信託積立ではドルコスト平均法を活用する
5-2.半年に1回は運用状況を確認する - まとめ
1.投資信託の積立、毎日と毎月どちらが良い?
毎日の積立と毎月の積立、それぞれのメリットや強みについて解説します。
1-1.運用成果はあまり変わらない
結論として、毎日または毎月の買付でも、ひと月の投資金額が同じであれば運用成果に大差はありません。毎日積立のほうが日々の価格変動の影響を受けますが、運用期間が長くなればなるほど買付価格が平準化(=偏りがなくなること)されるので、リターンや資産残高に大きな差は無くなっていきます。
それでは、毎日積立と毎月積立のシミュレーションをしてみましょう。日本を除く先進国の株価の値動きを示す代表的な指数「MSCIコクサイ・インデックス」に連動する投資信託に対して、毎日積立は、1日の積立額500円(土日祝日の休場日を除くと20営業日前後になるため)、毎月積立は、1万円の投資信託を月1回積み立てていくと、約10年後の運用結果は以下のようになります。
| 毎日積立 | 毎月積立 | |
| 積立額 | 500円 | 1万円 |
| 積立総額 | 101万500円 | 99万円 |
| 購入数口数 | 71万1544口 | 69万6696口 |
| 最終運用結果 | 223万8303円 | 219万1597円 |
| 収益率 | 121.50% | 121% |
※基準価額はYAHOO!ファイナンスを参照、信託報酬や税金等は考慮せずに算出
2015年12月~2024年3月末までの約10年間でリターンを比較すると、毎日積立の収益率が121.50%で毎月積立(121.37%)をわずかに上回りました。営業日数が異なるため、積立元本も同じではありませんが、最終評価額は4万円ほど毎日積立のほうが上回っています。
このほか、買付手数料や信託報酬などの運用コストも、買付金額や投資残高に対して発生するので、ここでも買付サイクルはあまり影響しません。したがって、積立投資の買付サイクルは、自分の投資スタイルに合わせて自由に選んでも差し支えないことがわかります。
1-2.積立頻度より運用期間の長さが大切
毎日500円(月20回)買付するのと、月1回買付して1万円の投資をするのとでは、投資成績に大きな差はありません。積立頻度を増やすほど、平均購入単価を引き下げる効果も期待できますが、運用結果に対する影響はやはり限定的です。
一方、投資信託の積立は、運用期間が長いほど最終的な評価額も多くなりやすい傾向にあります。日本経済は30年以上停滞したままですが、日本を除く先進国や新興国は経済成長を続けています。
さきほどご紹介した先進国株式の値動きを示す代表的な指数であるMSCIコクサイ・インデックスや、アメリカの代表的な株価指数S&P500に連動するファンドは、その恩恵を受けて基準価額の上昇が続いています。
月に同じ金額を積み立てる場合でも運用期間が短いほど時間的な分散効果を得られないほか、複利効果も得にくくなります。毎日積立もしくは毎月積立のどちらを選ぶにしても、大切なのは無理のない範囲で月にいくら投資するのかを決めて、長い運用期間を確保することなのです。
2.投資信託を毎日積立するメリットとデメリット
投資信託を毎日積み立てる場合に、考えられるメリットとデメリットをそれぞれピックアップしました。
2-1.毎日積立のメリット
心理的なバイアスを排除できる
毎日積立を行う場合、証券会社のWEBサイトなどで金額を決めて自動的に買付を行いますので、途中で積立頻度の変更などを行わない限り人間の判断が介在しません。機械的に決まった金額で買付できる分だけを購入していくのでので、結果として高い時は少なく、安い時は多めに買い付けることとなり、心理的なバイアスを排除し、より合理的な投資を行うことができます。
このドルコスト平均法による買付方法は、定額で積立投資を行う上で、大きなメリットとなります。
少額から投資できる
毎日積立のメリットは、少額からの投資ができることです。数百円から投資可能な証券会社も存在します。月に2万円まとめて投資するよりも、毎日500円程度の投資を続けるほうが経済的な負担も少なくていい方にとっては、心理的にも無理なく積立投資を継続することができるでしょう。
2-2.毎日積立のデメリット
残高が積み上がるまで収益が小さい
一括投資に比べて投資残高が少額ずつ積み上がっていく点は、積立投資のメリットですが、上昇相場の時に受けられる恩恵が少ないというデメリットもあります。年1回、年初の1月4日に100万円一括投資するのと、年末(12月30日)に100万円の積立投資が完了するのとでは、リターンおよびリスクが大きく異なるため、得られる収益に差が出やすくなります。一括投資のほうが利益も大きい可能性が高く、その代わり暴落時などには大きな損失を被る可能性も高くなります。
毎日積立や毎月積立はそのような下落相場の影響を受けにくい一方、残高が積み上がるまで収益も小さい点は弱点と捉えることもできます。
NISA枠上限まで使えない可能性
NISA口座を使って積立投資を行う場合、金額次第では上限枠まで使い切れないことがあります。
例えば、NISAのつみたて投資枠で毎月10万円ずつ買付すると、非課税枠上限の120万円となりちょうど良いのですが、割り切れない積立額に設定すると、使い切れないこともあるので注意しましょう。なお、積立額の途中変更は、多くの場合、各証券会社や銀行で設定可能なので、上手に調整して使い切ることが大切です。
3.投資信託を毎日積立できる主な証券会社
毎日積立のサービスを提供している主な証券会社の特徴を、以下の表にまとめました。どの証券会社も同程度のサービス内容ですが、SBI証券と松井証券が積立頻度、取扱本数に強みがあり、バランスの良いサービスを提供しています。つみたてNISAの取り扱いファンド数は、CONNECTと大和証券は少数ですが、その他のサービスでは200~220本程度と充実しています。
積立投資の場合、残高不足にならないようにスムーズな自動引落のサービスが求められます。各証券会社の自動引き落とし内容は、どの証券会社も自動引落サービスは揃えていますが、楽天証券では楽天グループの強みを生かした、楽天銀行や楽天カードとのシームレス連携に特徴が見られました。自動引落サービスの充実さも証券会社選択の際のポイントとなります。
※数値は2024年4月16日現在のものとなります。
| 証券会社 | 購入手数料 | 最低積立金額 | 積立頻度 | つみたて投資枠の取扱銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 無料 | 100円 | 毎日/毎週/毎月/複数日/隔月 | 224 |
| 楽天証券 | 無料 | 100円 | 毎日/毎月 | 222 |
| マネックス証券 | 無料 | 100円 | 毎月/毎日 | 219 |
| 松井証券 | 無料 | 100円 | 毎月/毎週/毎日 | 224 |
| CONNECT | 無料 | 100円 | 毎日 | 29 |
| 大和証券 | 無料 | 100円 | 毎日/毎週/毎月/隔月/3カ月毎/4カ月毎/6カ月毎 | 36 |
3-1.SBI証券

SBI証券の概要
- ゼロ革命の対象者は国内株式売買手数料0円
- 強力な高機能ツール「HYPER SBI」での取引が可能、スマホアプリにも対応
- IPO取扱銘柄数はトップクラス(2022年3月通期で117社の引受、全上場会社数のうち約97.5%の銘柄)
- 提携ポイントが豊富でポイ活・ポイント投資に強い(Vポイント・Tポイント・Pontaポイント・dポイントなど)
- PTS取引があるため夜間でも取引を行える
ユーザー数がネット証券でもトップクラスのSBI証券では、投資信託の積立日設定を5つから選べ、さらに年2回まで積立額の積み増しができる「ボーナス月コース」も用意しています(ただしクレジットカード決済ではいずれも選択不可)。
また、NISA取引の場合、投資可能枠の上限に合うよう自動で注文金額を調整してくれる機能や、NISA枠に収まらなかった買付分を自動で課税口座注文に変更してくれる機能も利用できるなど、高い利便性が強みです。
他にも、三井住友カードを積立に利用した場合には毎月の積立額に応じて最大5.0%のVポイントを貯めることが可能で、同様に東急カードでも最大3%のポイント還元が受けられるなど、高ポイント還元率も大きな特長です。さらにVポイントは投資信託のスポット購入にも利用できるので、積立購入と合わせて複利投資が可能です。
投信積立の管理アプリも充実しています。初心者の方でも始めやすい「積立スタイル診断」機能や、ファンドの損益および残高推移を手軽に確認できるなど、スマートフォンで完結する点も便利です。
3-2.楽天証券

楽天証券の概要
- 取り扱う金融商品が豊富である
- ポイントプログラムが充実、楽天カードや楽天銀行など他の楽天グループとお得に連携できる
- 国内株式(現物・信用)の取引手数料が無料、業界トップクラスの手数料の低さ
- 投資に関わる情報やコンテンツが豊富で取引ツールが充実
- 楽天FXが利用できる
SBI証券と並んで人気の高い楽天証券では、楽天ポイントを使って投資信託をスポット・積立購入できたり、楽天キャッシュや楽天カードクレジット決済が可能だったり、効率的に楽天ポイントを貯められたりするなど、楽天グループならではのサービスに強みがあります。楽天ポイントは1ポイント=1円換算で投資信託や国内株式(現物)、米国株式(現物・円貨決済)の買付に利用することも可能です。
投資信託の取扱本数、つみたて投資枠の取扱本数ともにSBI証券と双璧をなす高い充実度を誇り、特に楽天グループのサービスをよく利用する方に人気の証券会社と言えます。
3-3.マネックス証券

マネックス証券の概要
- 投資信託100円分から、毎日つみたて可、購入時申込手数料0円
- 投資信託を保有しているだけでポイントが貯まる、NISAも対象
- 国内株の手数料は税込55円から!定額コースも選べる
- IPOは初心者に嬉しい完全抽選制!NISAにも対応
- 外国株は米国株・中国株が購入可能、新興国ファンドや海外ETFも
マネックス証券の毎日積立の場合、つみたて投資枠では1月あたりの積立金額を設定することが可能です。指定した金額をその月のファンド営業日の日数で割った金額で、毎日(休業日を除く)買い付けてくれるため、手間もかかりません。非課税投資枠の上限に合わせた買い付けができるため、上手に使い切ることが可能です。
また、積立に必要な金額が証券口座内に無いなどのトラブルを防げる「つみたて定期自動入金サービス」も用意しており、設定すれば月々の積立額と同額を指定口座から証券口座に自動で振り込むことが可能になります。手数料もかからないため、便利なサービスです。
加えて、マネックス証券では投資信託を保有するだけでマネックスポイントを毎月受け取ることができます。投資信託の月内平均残高の最大0.08%(年率。銘柄により付与率が変わります)のポイントを獲得できるほか、マネックスカードで投信つみたて決済すれば、マネックスポイントの還元率が最大1.1%になるため、信託報酬などにかかるコストを実質的に削減できるのもユーザーにとって嬉しい点でしょう。
3-4.松井証券

松井証券の概要
- 株式取引で一日の約定金額50万円以下なら売買手数料無料
- 25歳以下は株式取引(現物・信用)のボックスレート手数料が無料(※1)
- 商品の種類が現物取引・信用取引での株式、IPO、立会外分売、投資信託、先物・オプション、FXなどと豊富
- 「ネットストック・ハイスピード」や「松井FP~将来シミュレーター~」などアプリやツールが豊富
- 銘柄探し・投資判断をサポートしてくれる電話窓口も
※1:一日信用取引、NISA口座・ジュニアNISAでのお取引、単元未満株の売却、立会外分売での買付、電話での取引は別の手数料体系
老舗ネット証券の松井証券も、SBI証券や楽天証券と並んで取扱ファンド数が多いのが強みです。投信積立における最も大きな特徴は、「投信工房」という投資一任型ロボアドバイザーを無料で活用できる点です。
ポートフォリオの選定に自信がない方でも、簡単な8つの質問に答えるだけでロボットが最適なポートフォリオを提案してくれるほか、基準価額の変動で偏った投資割合を自動で修正してくれる「リバランス積立」機能も活用できます。これによって、当初のポートフォリオからリスク性向をブレさせずに積立投資を継続できるようになります。
また、投資信託の保有残高に応じて付与されるポイント還元率の高さも業界最高クラスとなる最大1.0%です。貯まったポイント(松井証券ポイント)は、PayPayポイント、dポイント、アマゾンギフトカードに交換できます。
3-5.大和コネクト証券

大和コネクト証券の概要
- 1株から投資できる
- 業界最低水準の手数料体系
- ポイントを活用して運用を体験できる
- ポイントを株式に交換できる
- dポイントを貯められる
- クレカ積立がお得
CONNECTは大和証券グループの大和コネクト証券が提供するスマートフォン専用の投資サービスで、投資初心者の方にもわかりやすいインターフェイスが特徴です。取扱銘柄は少ないものの厳選されており、銘柄選びで悩む心配が少ない点はメリットとも取れます。
自動口座振替サービスで積立資金の不足を防げたり、NISA買い付け枠をオーバーした場合には自動的に特定口座で積立が継続されたりするなど、利用しやすさに強みがあると言えます。
3-6.大和証券

大和証券の概要
- 創業120年を超える歴史ある証券会社
- 全国に180以上の窓口
- オンライントレードの先駆
- 約300万人の利用実績
店頭証券会社大手の大和証券でも、投資信託を毎日積立することが可能です。こちらもCONNECTと同じく対応銘柄は厳選されているため、銘柄選びに悩む心配は少ないと言えます。
面談や電話の形で販売員に相談しながら取引ができる「ダイワ・コンサルティング」コースを利用しながら投信積立を行えるのがネット証券にはない大きな特徴です(ただし、購入はオンライントレードのみ対応)。
4.投資信託を毎日積立する場合、NISAのつみたて投資枠と成長投資枠のどちらがいい?
2024年1月から始まったNISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠のどちらでも毎日積立を行うことが可能です。成長投資枠は一括投資のみと誤認されていることもありますが、毎日積立、毎月積立を併用することが可能です。
新NISA(2024年1月から)
 ※画像引用:金融庁「NISAを知る」
※画像引用:金融庁「NISAを知る」
投資信託を毎日積立する場合、NISAのつみたて投資枠と成長投資枠のどちらがいいのか、それぞれの特徴を踏まえて活用方法を見ていきましょう。
4-1.色々な投資信託に投資したい場合は成長投資枠
成長投資枠のメリットは、つみたて投資枠のような厳しい基準が設けられておらず、投資上限も240万円と高い点が挙げられます。240万円の枠を全て積立投資に使うこともできますし、一部株式投資に回すこともできます。ある程度投資に慣れていて、運用計画を立てられる方にとっては成長投資枠のほうが資産運用をコントロールしやすいでしょう。
4-2.より長期の積立・分散に適したファンドを選びたい場合はつみたて投資枠
2018年1月に開始したつみたてNISAは、より多くの人に長期運用のメリットを享受してもらうための非課税制度として始まりました。
2024年1月に改訂された新NISAのつみたて投資枠についても従来のつみたてNISAと同様に、成長投資枠よりも投資上限枠を少なくし(120万円)、対象ファンドを限定的にすることで毎月少ない金額でも長期運用による資産形成がしやすいよう配慮されています。
つみたて投資枠はある程度、長期運用の道筋が建てられているので、NISA枠を長期運用に特化させたい方に向いています。また、つみたて投資枠のみでも非課税保有限度額の1,800万円の枠を使い切ることができるため、頻繁に売買を行う予定の無い方であれば、NISAの税制メリットを十分に受けることが可能です。
5.投資信託を長期視点で保有して資産形成をするコツ
長期運用で少しづつ資産を積み上げていくには、どのような点に気をつけると良いのでしょうか。ポイントを2つ解説します。
5-1.投資信託積立ではドルコスト平均法を活用する
積立投資を行う場合、決まった日に定額を積み立てる運用スタイルにしましょう。
定期定額積立(ドルコスト平均法)による分散投資の効果と投資効率の良さは積立投資の大きなメリットです。つい自分の考えで月々の投資金額をコントロールしたくなりますが、人間の感情を排除して機械的に投資を進めたほうが結果的には収益が上がりやすくなります。周期と金額のルールを守って積立投資のメリットを享受しましょう。
5-2.半年や1年で状況を確認する
目先の値動きに惑わされて、短期売買に陥ってしまうと長期運用のメリットを失ってしまいますが、かといって放置もよくありません。長期運用で着実に収益を積み上げていくには、定期的な運用状況の確認や見直しが必要です。
運用会社が毎月発行する月次レポートはファンドの商品紹介ページからでも確認できるので、相場が大きく変動した時や半年または1年に1回は全体的な資産の見直しを行うことが大切です。その時の生活スタイルに合わせて、毎月の投資金額を調整したり、新しく追加投資を行ったりするなど定期的な見直しは長期の資産形成に向けた有効な手段になり得ます。
まとめ
毎日積立は毎月積立と比べると運用成果にほとんど違いはありませんが、毎日少しずつお金を積み立てますので、生活スタイルに合わせやすいメリットがあります。月1回、まとまった金額を投資するには都合がつけにくい方にとって毎日積立は良い選択肢となるでしょう。
毎日積立ができる証券会社はいくつかありますが、クレジットカード決済やポイント還元率、自動引落機能等のサービスが充実しているとより便利です。証券会社選びに迷った時は、関連サービスの充実度を確認してみてはいかがでしょうか。
sayran
最新記事 by sayran (全て見る)
- AI関連の投資信託、成績や信託報酬など徹底比較【2024年6月】 - 2024年6月22日
- 投資信託の純資産総額、目安は?銘柄選びのポイントも - 2024年6月22日
- インドに投資できる投資信託・ETFは?主なファンド5本を比較 - 2024年5月28日
- 投資信託を毎日積立できる証券会社は?毎日積立のメリット・デメリットも - 2024年4月17日
- 三井住友DSアセットマネジメントのインパクトレポートの内容は? - 2023年7月17日