再生金融(ReFi)とは何か
ReFi(Regenerative Finance)とは、気候変動や環境破壊、貧困、不平等といった現代社会の課題に対し、金融の仕組みそのものを再設計することで持続可能な社会を築こうとする新たなアプローチです。従来の「成長のための金融」ではなく、「再生と修復のための金融」への転換を目指すこの動きは、環境・社会・経済のトリプルボトムラインを同時に改善する可能性を秘めています。
ReFiの土台には、ブロックチェーン、スマートコントラクト、DAO(自律分散型組織)などのWeb3技術があります。これにより、中央機関を介さずとも資金の流れを透明かつ信頼性の高いかたちで運用できるようになりました。資源管理やインセンティブ配布を自動化し、寄付型から脱却した経済的持続性のあるモデルが多数生まれつつあります。
ESGやインパクト投資と同様に、ReFiも社会課題の解決を志向していますが、決定的な違いは「誰もが起点になれる」点にあります。従来の金融は大口の投資家や企業中心でしたが、ReFiは市民や地域、スタートアップが直接的に公共財の創出に関与できる設計です。加えて、Web3技術によりインパクトの可視化とトラッキングが可能となり、グリーンウォッシングのリスクを回避できる点も評価されています。
ReFiの全体像を学べる最新レポート「ReFi Ecosystem Report 2024」
2025年1月にHEDGE GUIDEが発行した『ReFi Ecosystem Report 2024』は、世界のReFiプロジェクト100選を収録した業界初の包括的レポートです。ReFiの定義、技術的背景、サステナブル金融の流れ、関連プロジェクトの紹介、用語解説まで幅広く網羅し、初心者にも専門家にも有益な内容となっています。以下では、レポートより3つの特徴的なプロジェクトについてご紹介していきます。
Toucan Protocol:カーボンクレジットをオンチェーン化するインフラ
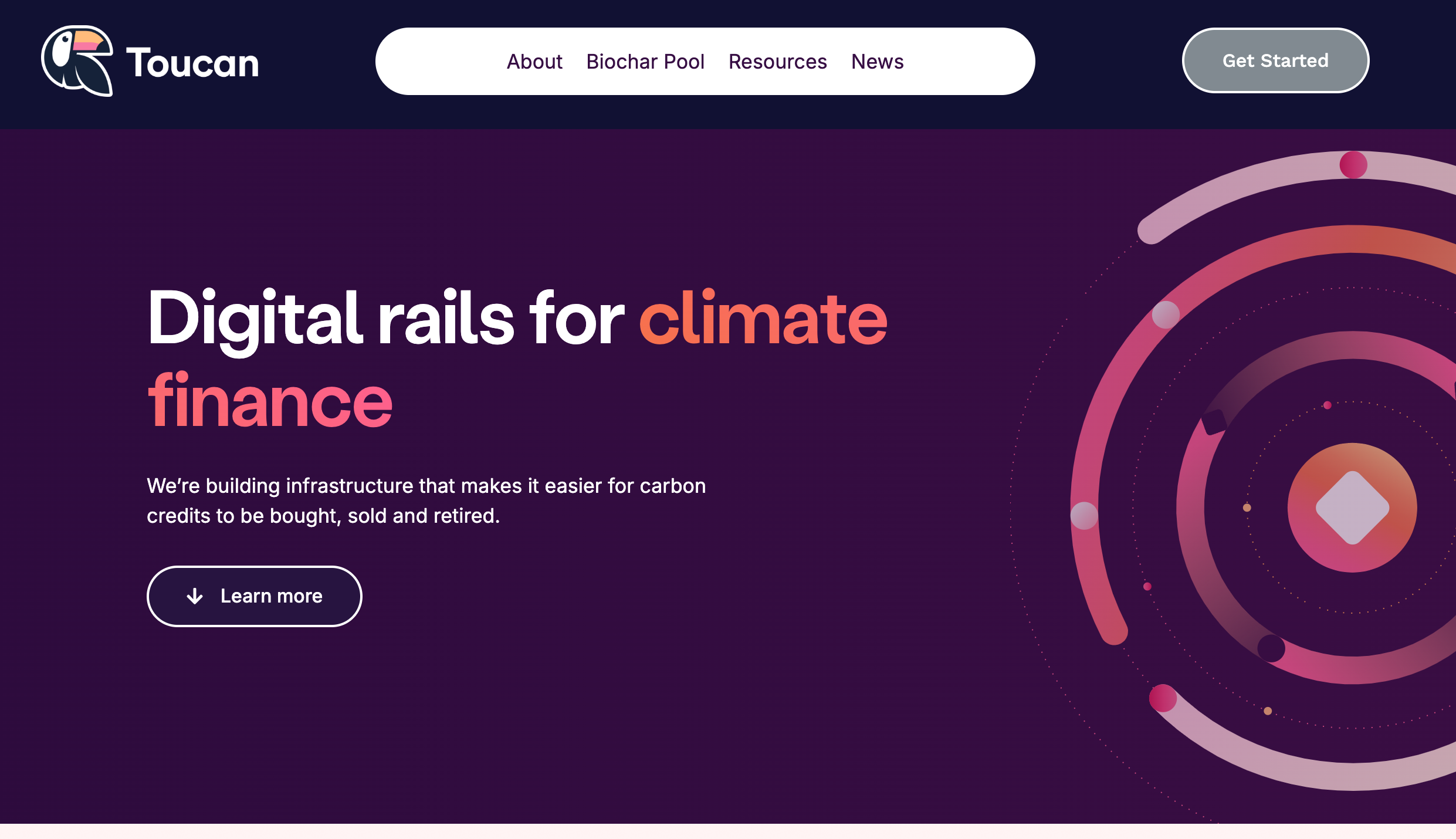
Toucanは、カーボンクレジット市場の透明性と流動性を高めるため、ブロックチェーン上での取引インフラを構築しているプロジェクトです。利用ブロックチェーンはCeloで、カーボンクレジットを「トークン」として表現し、取引・償却をオンチェーン上で管理できるようにします。従来、クレジットの売買には複雑な手続きと中間業者が必要でしたが、Toucanの登場により、誰もが容易に環境価値を流通させることが可能になりました。
本プロジェクトは、世界経済フォーラムやPuro.earthなどとも提携、ReFi領域での信頼性と実績を高めており、カーボンオフセットプロジェクトの事例として紹介しています。
EthicHub:小規模農家に金融アクセスを提供する分散型レンディング
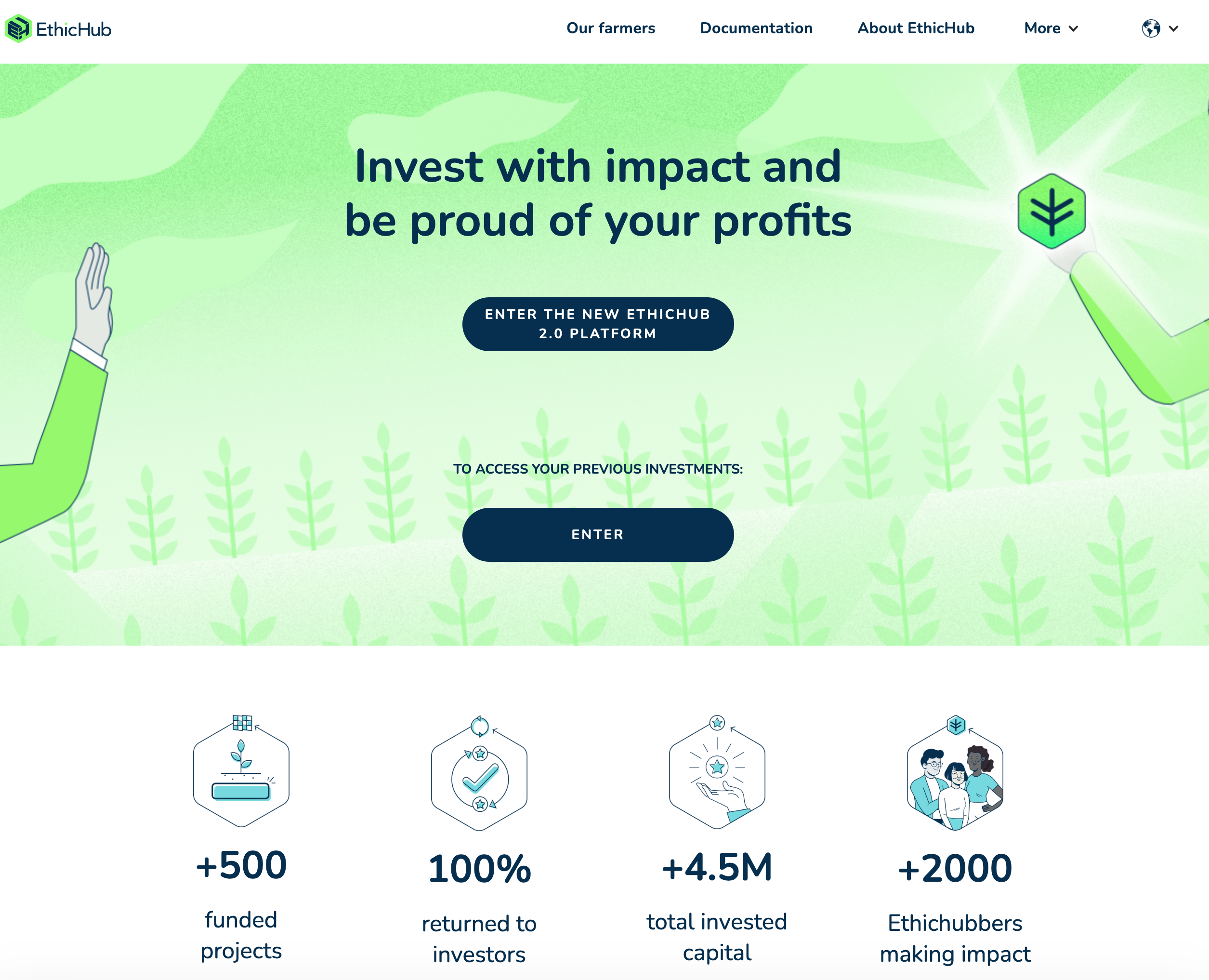
EthicHubは、メキシコをはじめとする途上国の小規模農家に対して、低金利で融資を行う分散型のクラウドレンディングプラットフォームです。Celoチェーンを活用し、支援者はトークンを通じて農家に資金提供でき、農家は中間業者を通さず直接支援を受けられる仕組みになっています。
興味深いのは、単なる「善意の融資」ではなく、農産物の生産性向上やフェアトレードの実現を通じて、持続可能な利益循環を設計している点です。リスクはコミュニティが分散して引き受ける構造となっており、DAOによる審査や信用スコアの導入も試みられており、レポートではマイクロファイナンスプロジェクトの事例として取り上げています。
MORI NFT:日本発の森林整備型カーボンクレジットプロジェクト
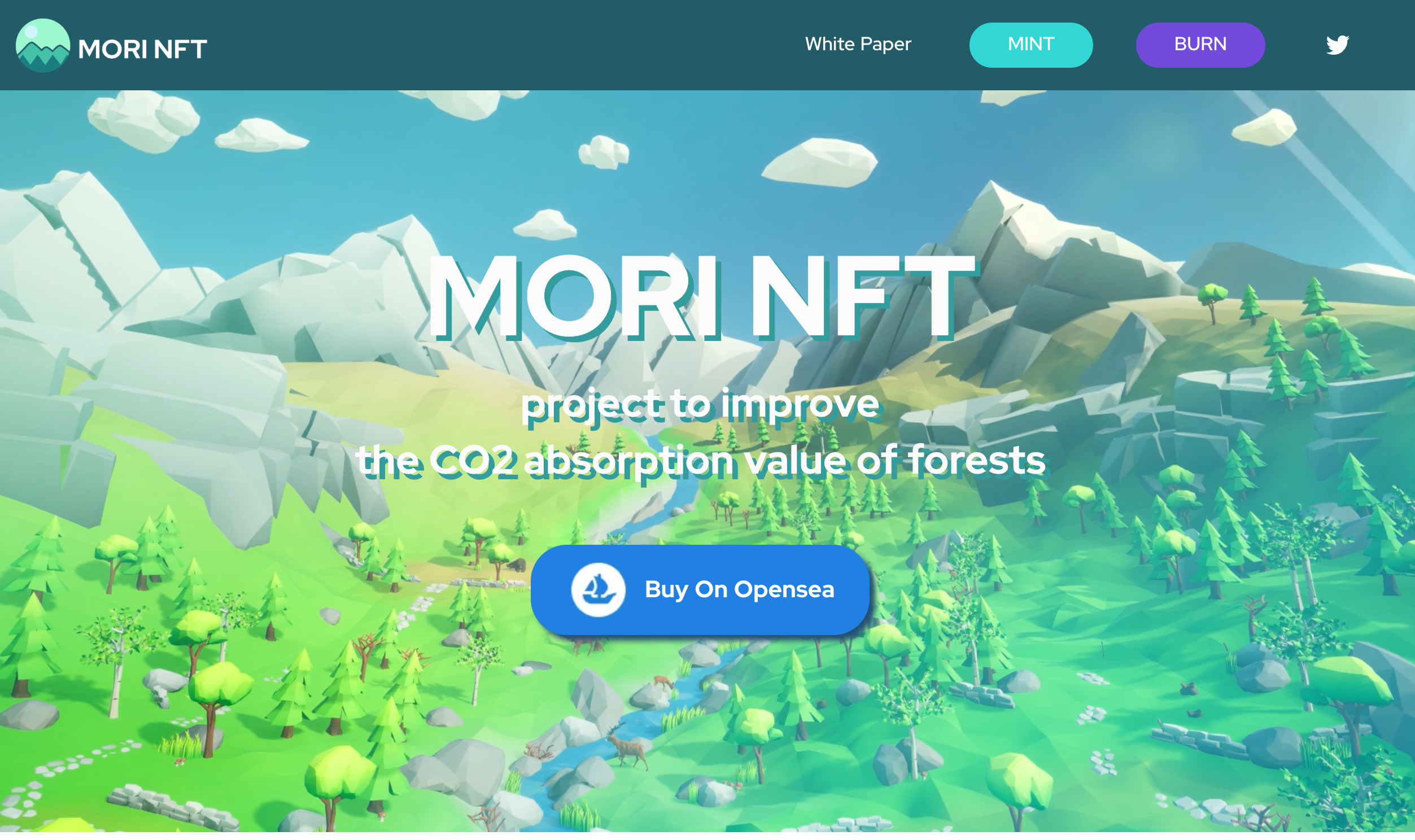
MORI NFTは、森林整備事業に基づいてNFTを発行し、CO2吸収量に応じたトークン「iGreen」がドロップされる仕組みを採用する、日本発のReFiプロジェクトです。イーサリアムをベースに構築されており、NFTを購入することで森林保全活動に直接貢献できる構造になっています。
特筆すべきは、日本国内のリアルな森林管理とWeb3技術を結びつけている点で、海外事例に偏りがちなReFi分野においてユニークな存在となっています。資金は運営費を除きすべて現地の森林整備に充てられ、環境保全の新たな資金調達モデルとして期待されています。
ReFiが開く個人参加型の持続可能な社会への道
本記事で見てきたように、ReFi(再生金融)は気候変動や社会的不平等といった構造的課題に対する新たなアプローチを提供しています。従来の持続可能性への取り組みは、消費の抑制、環境税の負担、高価なエコ製品の購入など、個人にとって「コストがかかる」「便利さを諦める」という側面を持っていました。また、ESGやインパクト投資は長らく制度的・資本的な整備が進んだ分野ですが、個人が参加するには一定の専門知識や資金が求められるため、接点を持ちづらいケースも少なくありません。
これに対しReFiは、参加者に明確な経済的インセンティブをもたらしながら社会課題の解決に貢献できる仕組みを実現しています。省エネのような「節約型」ではなく、積極的に「創出型」の活動に報酬が得られる点が大きな転換です。
特筆すべきは、これまで大企業や機関投資家、政府主導で進められてきた環境・社会課題の解決に、個人が直接参加できるようになった点です。Toucan Protocolを通じたカーボンクレジットへの関与、EthicHubによる小規模農家への直接支援、MORI NFTによる森林保全への参画など、Web3技術の活用により、市民一人ひとりが自分の関心や価値観に基づいて行動し、その貢献に応じた報酬を得られるようになりました。数百万円単位の株式投資や専門知識がなくても、数千円から始められる点も参入障壁を大きく下げています。
この「自己犠牲ではなく、インセンティブによる前向きな参加」というアプローチは、持続可能な社会の実現において重要な転換点となる可能性があります。環境保全や社会貢献が経済的利益と対立するものではなく、むしろ相乗効果を生み出す形で設計されることで、より多くの人々の積極的な参加を促すことができるのです。
日本においても、すでにMORI NFTなどの取り組みが始まっており、森林管理や地方創生などの分野で個人が気軽に参加できる形でのReFi応用が広がりつつあります。『ReFi Ecosystem Report 2024』は、これらの最新動向を知り、自分自身がどのように参加できるのかを理解するための貴重な資料としうていただけると幸いです。
ReFiは、環境問題や社会課題の解決を「誰かに任せるもの」から「自分も参加して利益を得るもの」へと変える可能性を秘めています。持続可能な社会の構築に関心を持つすべての人々にとって、ReFiは新たな行動の選択肢を提供してくれるはずです。
HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム
最新記事 by HEDGE GUIDE 編集部 Web3・ブロックチェーンチーム (全て見る)
- 「ReFi」とは?Web3で変わるサステナブル金融の未来 - 2025年5月21日
- DIMO、HAKUHODO KEY3と提携 日本市場で自動車データの新しい未来を築く - 2025年3月26日
- ReFiで広がるカーボンクレジット市場の未来― KlimaDAO JAPANの取り組みと展望【インタビュー】 - 2025年3月14日
- ReFi×インパクト投資×システミックデザインから見る、新しい経済システムと金融の未来(HEDGE GUIDE / IDEAS FOR GOOD Business Design Lab) - 2025年2月12日
- peaq、次世代AIインフラ企業iGam3の参加を発表 計算基盤の分散化で新たな経済圏へ - 2025年2月5日
















